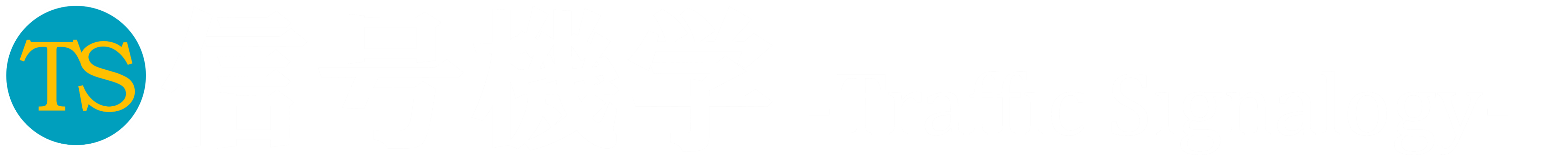当サイトで用いる信号機用語について解説します。当サイトでは信号機マニア間で一般的に用いられる呼称や略称を採用するようにしています。順次追加していきます。
■ あ行
あ
い
う
●宇宙人(うちゅうじん)
| 京三製製作所の初期丸型灯器。昭和45年頃から昭和55年頃にかけて製造された。丸みを帯びた筐体にレンズが縁ギリギリに収められている外見がリトルグリーンメンのようなエイリアンを思わせることからこの呼称がついたらしい。 |
●渦巻レンズ(うずまきれんず)
| 小糸工業の西日対策レンズ。内側に挟まれた同心円状の遮光板によって擬似点灯を防止する機能がある。鉄板灯器時代から西日対策に積極的であった都道府県を中心に設置された。 |
え
お
●おまる
| 京三製作所のアルミ灯器。蒲鉾の次の世代の一体型灯器で、平成14年から5年程製造された。電球式とLED式の兼用モデルで、厚型筐体としては最終型となる。背面に四角錘台状の凸部があるのが特徴。 |
■ か行
か
●角型灯器(かくがたとうき)
| 直方体の筐体で、基本的に古い世代の灯器。メーカーごと構造やレンズは異なるものの、外観や設置方法は類似している。更新対象であるので、現在では一部の県でしか見られない。 |
●蒲鉾(かまぼこ)
| 京三製作所のアルミ灯器。分割型の次の世代にあたる一体型灯器で、平成11年から4年程製造された。背面に蒲鉾状の凸部が3つあることが由来。電球式が主だが、LED式のものもある。 |